|
 |
|
| 哲治先生は生涯画家と名乗ることも、また人にそう呼ばれることも良しと |
| しませんでしたが絵画への真摯な取り組みと、残された数多くの作品は絵を描く |
| ものとしての天性を感じさせた。 |
| |
| 世間的な名声を求めず、「街の美」を題材にひたすら自分の描きたい絵を描き続けた。 |
| 昭和14年から始めた個展は28回開催され、そのて展示作品は1.000点以上とも |
| いわれている。 |
| |
| 明治36年、九戸郡軽米町にて次男として生まれる。 |
| 芸術家で多趣味な父のもとで育ち、小さい頃から絵が得意だった |
| 哲二先生は岩手県立盛岡工業学校機械科卒業後、陸軍省航空廠 |
| 所沢製作所に入り製図等 の仕事をする傍ら |
| 太平洋画会研究所に入所し鶴田吾郎、石川寅治らの指導を 受ける。 |
|
| しかし栄養失調から体をこわし、1年余で帰郷。その後も故郷で代用 |
| 教員などを務めながら、夏休みなどに上京して研究所やその他の |
| 講習に通いました。 |
| 大正12年から地元の七光社展、昭和4年には素顔社展に出品。 |
| ※七光社(ななこうしゃ) 岩手洋画発展の功労者「清水七太郎」 |
| らが結成 |
|
|
 |
| ・昭和5年 黒沢尻高等女学校嘱託教諭 |
母校校舎
西側から望む |
|
| ・昭和8年 岩手中学校嘱託教諭 |
| ・昭和9年 岩手教員会嘱託、岩手教育「小学校練習帳」表紙を担当 |
| ・昭和12年 平館清七、荒浜栄悦らと「岩手教育美術協会」設立 |
| ・昭和16年 第7回太平洋画展で入選 |
| ・「岩手美術連盟」を結成、幹事に就任 |
| ・昭和22年 「盛岡市内高等学校美術連盟」を海野径と共に結成、顧問となる |
| ・昭和23年 岩手中・高等学校教諭に任命 |
| 教え子には美術関係に進んだ者も少なくありません。 |
| |
| 30代までは中央の展覧会にも挑戦、入選も果たしましたが、仕事の合間に作品を描き |
| あげ、それを東京まで運搬するのに手間がかかることもあって、戦後は中央への出品 |
| は止めてしまいました。 |
| 忙しい務めの合間をぬっての制作でしたが、亡くなるまで開いた個展は通算28回。 |
| |

|
| 「自然に向っていればすべて忘れられる」と言っていた哲二先生の |
| 作品はほとんとが風景画で、大きいものでもせいぜい30号。 |
| 家にアトリエがあるわけでもなく、おのずと足は外へ向かいました。 |
| 小品主体ながらキャンバス擬縮された表現、温かみを保ちながら |
| 甘さに流れない筆致。色彩の豊かさで長年のうちに沢山のファンが |
| 生まれた。 |
|
| 和44年に定年退職。昭和56年、前年77才で世を去った哲二先生を |
| 偲んで画友や教え子達が企画した「追悼の小笠原哲二展」では |
| 300点近い油彩が会場を埋め、多くの鑑賞者を集めました。 |
|
|
| 岩手美術連盟幹事、岩手県高校美術連盟顧問など歴任して岩手の美術関係の |
| 発展と指導にあたられました。 |
|
| 石桜同窓会会報への投稿作品 |
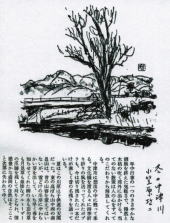
|
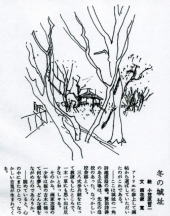 |
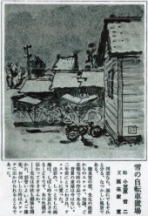 |
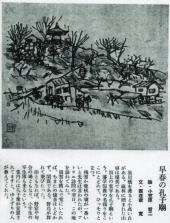 |
冬の中津川
会報 昭和47年 第7号 |
冬の城址
会報 昭和49年 第8号 |
冬の自転車置き場
会報 昭和50年 第9号 |
早春の孔子廊
会報 昭和51年 第10号 |
<拡大写真> 写真をクリックし拡大してご覧ください |
| |
|
| |
| |小笠原哲二先生の詳しい年表| |
| |